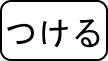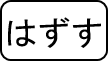-
カテゴリ:全体
令和6年度学校評価結果 -
※学校概要にて掲載していましたが、こちらに再掲載します。
令和6年度の学校評価結果をお知らせします。
保護者の皆様からの評価や、こどもたちの状況を基に、さらによりよい学校づくりに向けて、改善を進めて参ります。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
公開日:2025年04月21日 15:00:00
更新日:2025年04月21日 16:25:33
-
カテゴリ:全体
給食室から(十五夜) -
今日は十五夜につなんだ給食です。
公開日:2021年09月21日 15:00:00
-
カテゴリ:全体
給食室から(重陽の節句) -
9月9日の「重陽の節句」にちなんだ給食です。
公開日:2021年09月10日 12:00:00
更新日:2021年09月10日 13:06:21
-
カテゴリ:全体
こころとからだのひろば(スクールカウンセラーから) -
今回のテーマは、「緊張(きんちょう)」です。
みなさんは、どういう時に「緊張」している自分に気付きますか?発表をしなければならない時、自信がもてない活動を行う時など、人によって緊張しやすい場面は違います。
けれど、緊張している時には、体の筋肉(きんにく)が緊張している、ということは共通です。そこで、筋肉の緊張を和(やわ)らげることで、こころも含む「緊張」をゆるめる、というアプローチがあります。
【手順】
1 目をつぶって、息を吸います。
2 全身に力を入れて、筋肉を緊張させます。
頭、首、肩、腕、手、胸、お腹、背中、お尻、ふともも、ふくらはぎ、足首、と体全体を緊張させます。
3 そのまましばらく息を止めます。
4 息を吐きます。同時に体中の力を抜きます。
5 体がリラックスした状態を感じながら、ゆっくり呼吸を続けます。
全身に力を入れることができない場面もあるかと思います。そういう場合は、ご自宅などでこの手順を行ってみて、力を抜く感覚、身体の緊張を緩(ゆる)める感覚を体験してみてください。
その感覚がつかめれば、以降は、手をぎゅっと握りしめた状態をしばらく続けてから一気に力を抜く、肩に力を入れてからストンと脱力する、など小さな動きでも代用できるようになります。わざと過剰(かじょう)に力を入れて体を緊張させ、その力を抜くことでリラックスした感覚を体感する方法です。吸うことよりも吐くことを長めにした、ゆっくりとした呼吸とともに、お試しください。
公開日:2021年09月09日 15:00:00
更新日:2021年09月14日 17:51:01
-
カテゴリ:全体
こころとからだのひろば(保健室の先生から) -
7月の保健室の掲示物は、「元気のパワーを満点にしよう。こんなときはどうする?」です。
食欲がない時、気分が落ち込んでしまった時、目が疲れた時、外で元気にあそぶ時 など
夏に多く起こる、体調がすぐれない、いろいろな時、上手に対応して、元気に夏を過ごしましょう。
公開日:2021年07月06日 08:00:00
更新日:2021年07月07日 19:05:02
-
カテゴリ:全体
給食室から(給食聖火リレー 静岡県) -
東京オリンピック・パラリンピック2020まで、あと1ヶ月となりました。
昨日(23日)は静岡県特産の桜えび、しらす干し、黒はんぺんを給食で味わいました。
公開日:2021年06月23日 16:00:00
更新日:2021年06月24日 12:41:50
-
カテゴリ:全体
給食室から(かみかみ給食) -
6月4日から今週木曜日の6月10日までは、「歯と口の健康週間」です。
そこで、今日の給食は「かみかみ給食」でした。
みなさんは、自分が食事をする時に何回くらいかんでいると思いますか?1回の食事でだいたい600回くらいかんでいると言われています。
昔の日本人が1回の食事で何回かんでいたかを、いろいろな資料から調べたデータがあります。
今から約2000年前の弥生時代の 卑弥呼は・・・3990回!
約850年前の 鎌倉幕府最初の将軍 源頼朝は・・・2654回!
約450年前の 江戸幕府を開いた徳川家康は・・・1465回!
そして、現代の私たちが約600回です。
なんと、卑弥呼は私たちの6倍以上もかんで食事をしていたそうです。「かむ」ことは、体にとってたくさんの良いことがあります。太りすぎないようにする、味をしっかり感じるようにする、言葉がはっきり言えるようにする、脳を発達させる、食べた後の消化を良くするなどです。
「ひみこの歯がいーぜ」で覚えてください。
公開日:2021年06月07日 16:00:00
更新日:2021年06月07日 20:08:25
-
カテゴリ:全体
給食室から(給食聖火リレー 富山県) -
東京オリンピック・パラリンピック大会の聖火リレーで回る地域の料理にちなんだ給食です。
公開日:2021年06月05日 11:00:00
-
カテゴリ:全体
こころとからだのひろば(保健室の先生から) -
今月(こんげつ)の保健室前(ほけんしつまえ)の掲示板(けいじばん)は、歯(は)についてです。
むし歯(ば)がどのようなしくみでできるのかをイラストをひらいて見(み)てみましょう。
また、歯科検診(しかけんしん)の結果(けっか)や自分(じぶん)の口(くち)の中(なか)を見て自分(じぶん)の口の中の健康状態(けんこうじょうたい)を知(し)り、じょうずな歯(は)みがきを身(み)につけましょう。
公開日:2021年06月04日 09:00:00
更新日:2021年06月04日 12:52:53
-
カテゴリ:全体
給食室から(給食聖火リレー・広島県) -
前回からお伝えしている、聖火リレーで回る各地の料理です。今日は「広島県」です。
公開日:2021年05月17日 19:00:00